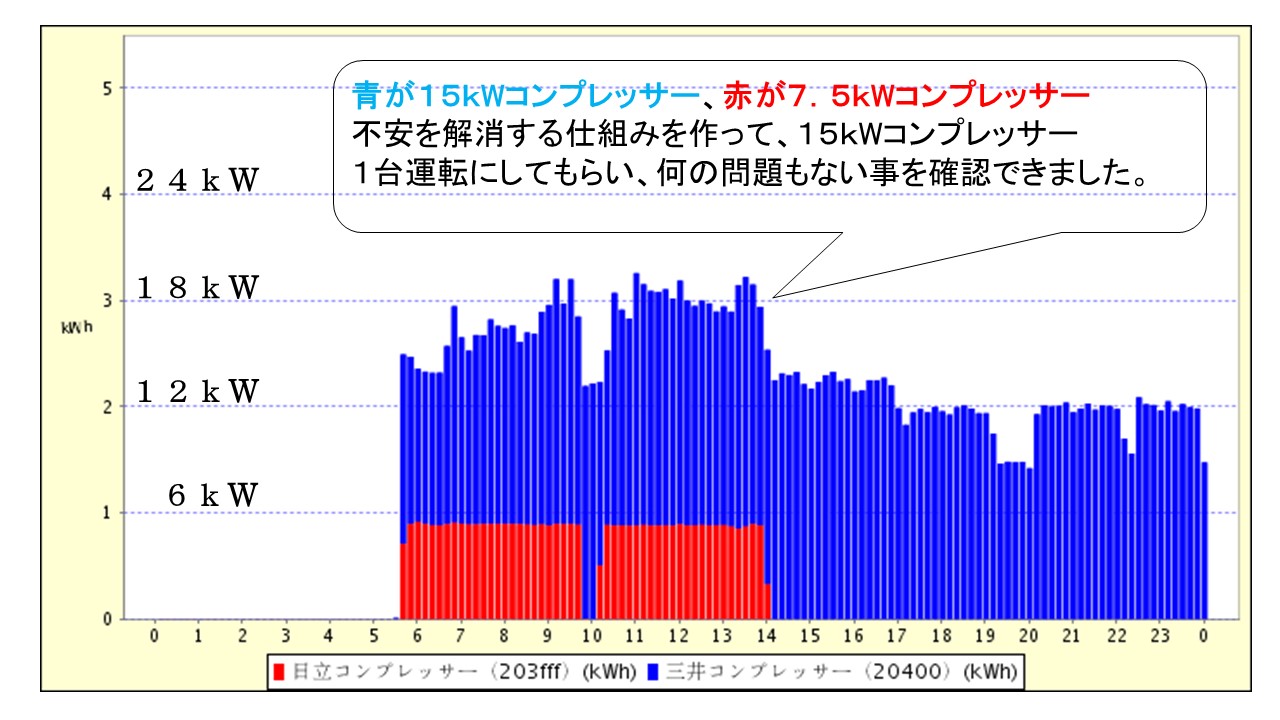先般、多摩大大学院でご指導戴いた田坂広志教授が、大阪変革塾の開塾に当たり、
ホームページに塾頭メッセージを出されました。(本ページ最後に転載しています。)
この中の一文が心に留まりました。
【「マネタリー経済」偏重の従来の資本主義のパラダイムを超え、全国の地域において、「ボランタリー経済」を活かし、「目に見えない資本」を活用していく「日本型資本主義」の復活を実現していく】
「目に見えない資本」
この言葉の指すものとして、「知識資本」、「関係資本」、「信頼資本」、「評判資本」、「文化資本」が、田坂広志先生のご著書「目に見えない資本主義」で語られています。
http://www.amazon.co.jp/%E7%9B%AE%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E8%B3%87%E6%9C%AC%E4%B8%BB%E7%BE%A9-%E7%94%B0%E5%9D%82-%E5%BA%83%E5%BF%97-%E3%81%9F%E3%81%95%E3%81%8B-%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%97/dp/4492395180
直近の自分の営業活動を振り返り、ある考え方を変える機会を戴きました。
今、5月11日(月)から応募の始まる環境省の補助金「平成27年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(経済性を重視した二酸化炭素削減対策支援事業)のうち二酸化炭素削減ポテンシャル診断事業」( http://lcep.jp/offering.html )を活用して省エネ診断を行うお客様を開拓する営業活動をしている真最中です。
この補助金は、省エネ診断を希望する事業者が、弊社のような診断機関を活用して省エネ診断を行なった場合に、上限を超えない範囲で全額を補助するというもので、省エネ診断を希望するお客様にとっては、自己負担ゼロで省エネ診断を受けることができ、省エネ対策の提案を獲得できるものですし、弊社のような診断機関にとっても、ご採用戴くためのハードルが低くなるという点で、大変大きなチャンスとなります。
こうした中で目にした「目に見えない資本」、そして、「評判資本」という言葉。
「今、自分は、この補助金を利用して、楽に売上げを得ようとしているのではないか?」との疑問が湧き上がるとともに、この補助金事業のタイトルに含む「経済性を重視した二酸化炭素削減対策」との言葉に考えさせられました。
弊社の「電力見える化」機器を活用しての省エネ診断・コンサル・サービスは、まさに「コストパフォーマンスの高い省エネ手法」で、その良さを、お客様は勿論、環境省や事務局の三菱総研さんに知って戴き、「評判資本」を獲得することこそが、弊社にとって、この補助金事業に参画する意味なのではないかと気が付きました。
(環境省が示している「経済性を重視した二酸化炭素削減対策」とは、この診断事業自体を指しているものではなく、「診断で提案される削減策が、高い経済性のものを」との意ではあろうかと思いますが、この診断自体を含めての言葉と解釈することに致しました。)
この補助金事業に参画するという「やること」自体は同じでも、「どのような心の姿勢で臨むのか」が違ってきますと、行動も全く違ったものになろうかと思います。
「楽に売上げを得よう」との考えであれば、おそらくお客様に提供するサービスのコストパフォーマンスを最大にすることを目指さずに、補助金の上限まで獲得しようと腐心することになろうかと思います。
しかし、「コストパフォーマンスの高い省エネ手法」の良さを、皆さまに知って戴き、「評判資本」を獲得することを目指すことに変更した今、お客様にとって、コストパフォーマンスの高い省エネ・サービスをご提供するという、補助金無しの通常の事業活動と全く変わらぬ姿勢で取り組むことができるようになれると思えます。
「電力見える化」機器を活用しての省エネ診断・コンサル・サービスの有効性を皆さんに知って戴き、「評判資本」を獲得できることに繋がり、ひいては、エネルギー問題の解決に微力でも貢献することに繋がればと、全力を尽くして取り組みたいと考えます。
【「マネタリー経済」偏重の従来の資本主義のパラダイムを超え、全国の地域において、「ボランタリー経済」を活かし、「目に見えない資本」を活用していく「日本型資本主義」の復活を実現していく】
「マネタリー経済」の産物である補助金事業の中で、「目に見えない資本」の内の「評判資本」を生み出すことができるのか?の、小さな小さな実験でもあります。
****************************************************************************************************
【大阪変革塾 田坂広志 塾頭メッセージ】
http://www.osaka-jc.or.jp/leader/lecturers/
いま、この日本という国に求められているのは、ただ、社会変革のビジョンを語り、政策を語るだけの「評論家的人材」ではない。求められているのは、「思想」「ビジョン」「志」「戦略」「戦術」「技術」「人間力」という「七つの知」を垂直統合した人材、目の前の「現実」を粘り強く変革していく「知の力」を持った「真の変革者」に他ならない。
そして、この国の変革は、「東京一極集中」という歪なこの国の在り方を変え、全国津々浦々の地域が、それぞれに個性的に輝くという国の在り方を実現することから始めなければならない。
では、全国の地域が「個性的に輝く地域」となっていくために、いま、我々は、何を為すべきか?
そのためには、まず、「マネタリー経済」偏重の従来の資本主義のパラダイムを超え、全国の地域において、「ボランタリー経済」を活かし、「目に見えない資本」を活用していく「日本型資本主義」の復活を実現していくことであろう。
そして、同時に、地域の経営の現場では、世界に誇るべき「日本型経営」を復活させ、高き志と使命感を抱き、日々の仕事を通じて社会変革をめざす「日本型社会起業家」を育成していくことであろう。
この「大阪変革塾」は、そうしたビジョンと戦略に基づき、全国津々浦々の地域から我が国の変革の巨大な運動を引き起こすべく、その「真の変革者」を育成する場として、活動を開始する。
いよいよ始まる、この国の変革、その「真の変革者」として、この歴史的な変革の運動への参加を希望する諸氏は、いま、この「大阪変革塾」への入塾を。