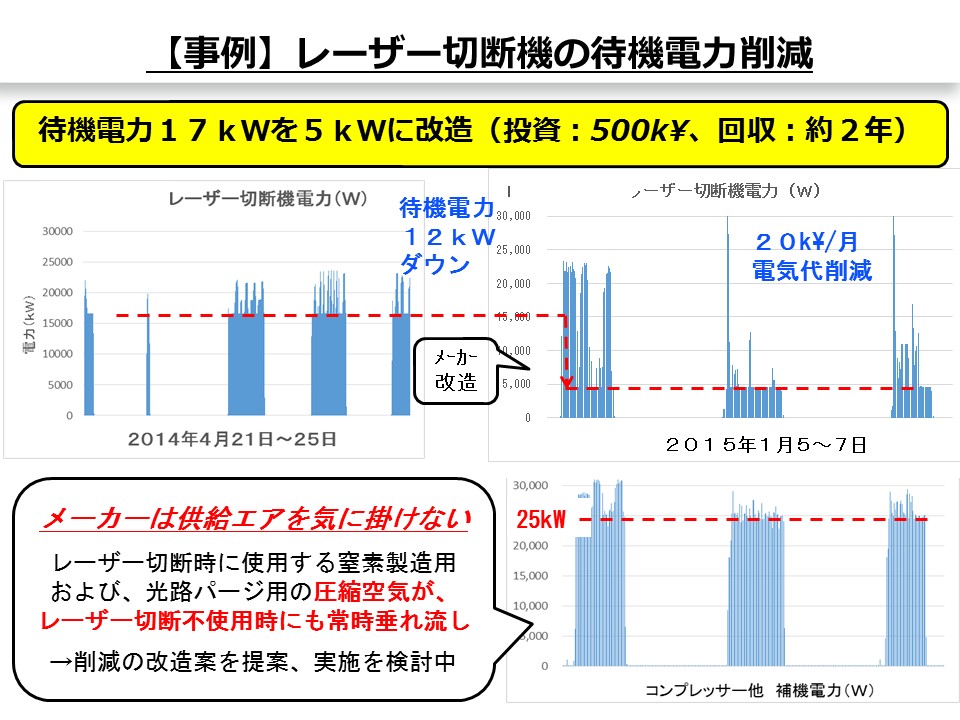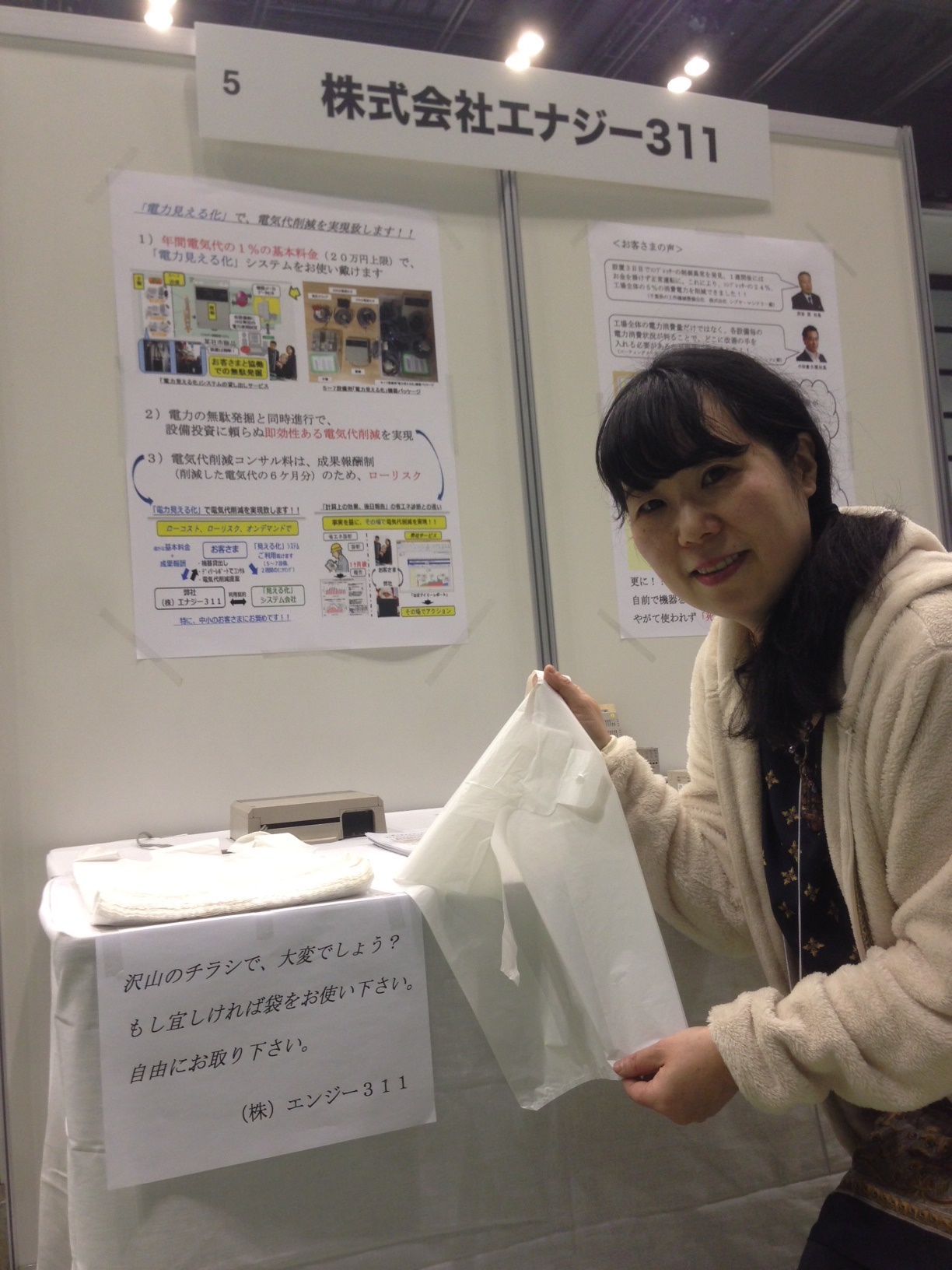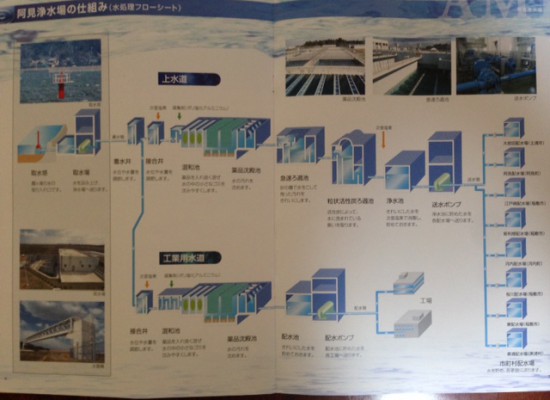弊社では、「電力見える化」で得られた実測データを元に、光熱費削減のご提案をしております。
世の中には、「電力見える化」機器を販売するメーカーが数多くありますが、それらのメーカーも、機器を購入するお客様も、ある「錯覚」を持っておられる方が多くいらっしゃるのではないかと感じております。
その「錯覚」に相通じると感じました記述を、多摩大学大学院の田坂広志教授の「なぜ日本企業では情報共有が進まないのか」の中で見つけましたので、ご紹介させて戴きます。
(引用)
私が申し上げたいのは、これから(注:この本は1999年発刊)の企業情報化の嵐のなかで生き残れないのは、「パソコンができないマネージャー」ではなく、「豊かな知識や深い智恵を持たないマネージャー」が生き残れないということなのです。
そもそも、私が、「パソコンができないマネージャーは生き残れない」という議論を批判する理由は、こうした短絡的な議論が、多くのマネージャーのなかに、ある種の「錯覚」を生み出してしまうからなのです。
その「錯覚」とは、「パソコンができるようになれば生き残れる」という錯覚です。
(引用終わり)
「電力見える化」機器を販売するメーカーや、機器を購入するお客様が陥る「錯覚」とは、今流行の「電力見える化」機器を導入さえすれば、電力管理が強化される、何か有益な光熱費削減効果が得られるという「錯覚」です。
これから訪れるであろうデマンドレスポンスやスマートシティの世界についても、同様に思えます。 世の中では、しきりに、そのシステムについては論じられますが、そこには人が不在のように感じます。
しかも、人と言いましても、単に情報技術や電力技術に長けたシステム・エンジニアがいれば、夢のような電力システムが産まれるということではなくて、対象となる現場に関しての豊かな経験や知識、深い智恵を持っている人が介在しないと機能しないであろうということです。
1)「電力見える化」機器を販売するメーカーには情報技術に長けた技術者がいます。
2)省エネ診断を生業とする人たちは、省エネ技術に長けています。
3)お客様の現場には、その現場特有の技術に関する豊かな経験や知識、深い智恵を持った技術者がいます。
「電力見える化」機器を使って、光熱費を削減しようとする時、この3者の誰が欠けても、上手く機能するものではないだろうと考えます。
弊社は、この3つ全てのトップランナーというわけではございませんが、この3つをあるレベルでハンドリングし、「電力見える化」で得られた実測データを元に、お客様にとってコストパフォーマンスの高い光熱費削減施策をご提案致します。
1)「電力見える化」機器の運用技術
2)省エネ技術者としての知識や経験
3)製造現場での長年の実務経験で得られたノウハウ
この特長を活かして、必ずしもお客様にとってコストパフォーマンスが高いとは限らない省エネ設備を販売するサービスとは異なる、お客様にとってのベストチョイスの省エネ施策のご提案でお客様の光熱費削減に寄与したいと考えております。
そして、この事業を通して、これからやってくるデマンドレスポンスやスマートシティの社会が、無機質な情報システムや電力システムだけが広まる社会ではなく、現場の豊かな経験や知識、深い智恵が活かされる社会となるための一助になれればと考えております。
引用書籍 「なぜ日本企業では情報共有が進まないのか」(田坂広志 著)
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%AA%E3%81%9C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%A7%E3%81%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%81%8C%E9%80%B2%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B%E2%80%95%E3%83%8A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC7%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%BF%83%E5%BE%97-%E7%94%B0%E5%9D%82-%E5%BA%83%E5%BF%97/dp/4492553401